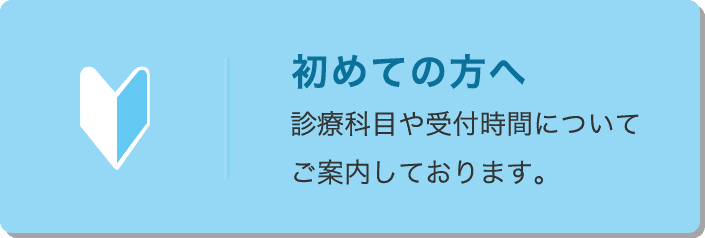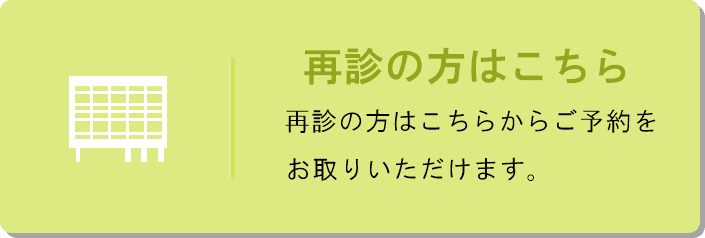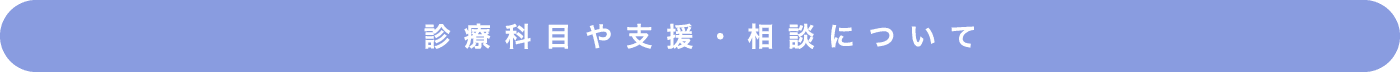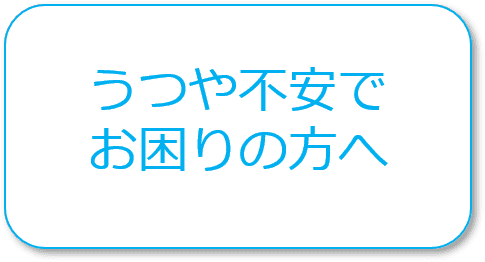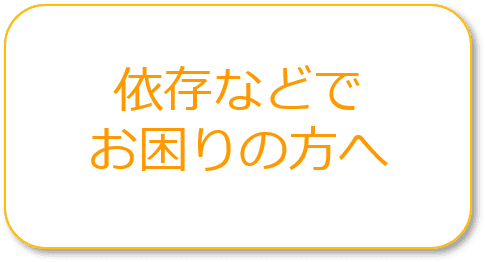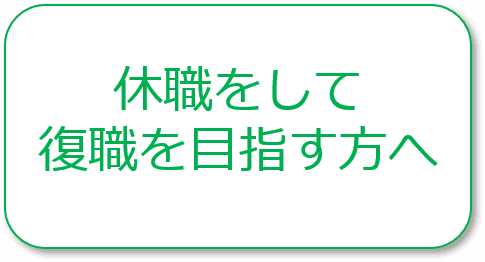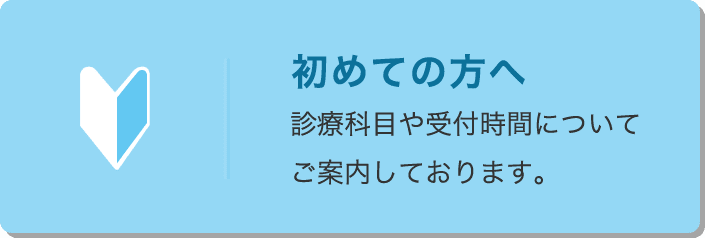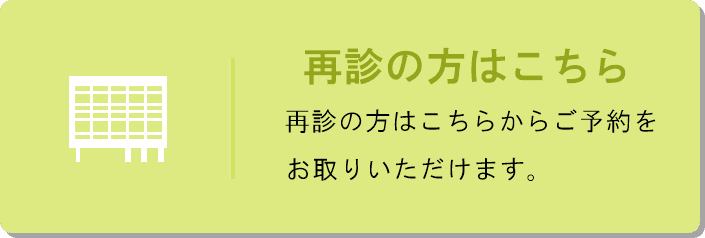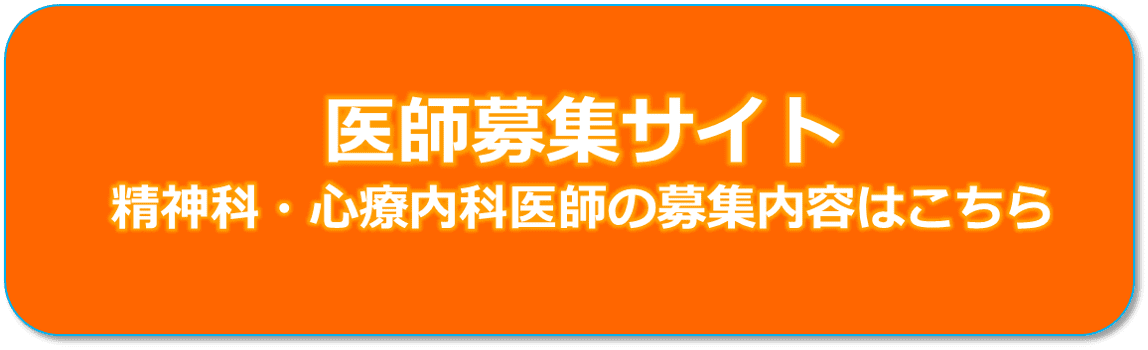院長あいさつ

院長 山﨑 聞平
人生は旅です。
たった一回きりの人生を、自由に存分に生きられるような社会であってほしいと思います。
しかし、現実は理不尽なことが尽きず、風雪は止まず、山あり川あり砂漠ありです。
自分が信じられなくなり、他者が信じられなくなり、先が見通せなくなったとき、
こころの不調が生じてきます。
人はその意志に関係なくこの世に産み落とされました。
現在に至るまで、その過程には家族、友人、仕事などが関わってきます。
つまり、こころの問題が生じた時はもはや、その人だけの問題とはいえません。
残念ながら、心療科、精神科が扱うこころの病気は、体の病気のように生物学的・身体的な原因がはっきりわかっているものは多くありません。
たった一回きりの人生を、自由に存分に生きられるような社会であってほしいと思います。
しかし、現実は理不尽なことが尽きず、風雪は止まず、山あり川あり砂漠ありです。
自分が信じられなくなり、他者が信じられなくなり、先が見通せなくなったとき、
こころの不調が生じてきます。
人はその意志に関係なくこの世に産み落とされました。
現在に至るまで、その過程には家族、友人、仕事などが関わってきます。
つまり、こころの問題が生じた時はもはや、その人だけの問題とはいえません。
残念ながら、心療科、精神科が扱うこころの病気は、体の病気のように生物学的・身体的な原因がはっきりわかっているものは多くありません。
ですから、症状だけでなくその人の背景・歴史を理解することが重要です。
当院では医師・看護師・公認心理師・臨床心理士・精神保健福祉士・作業療法士などの専門職三十数名のスタッフが、みなさまを一人の「歴史ある人間」としてとらえ、専門家としての助言を行いながら対等な立場で「生きる」ことをサポートします。
そして、みなさま一人ひとりが人生の旅を続けられるように、メンタルヘルスの面からサポートすることができるように尽力する所存です。
よろしくお願い申し上げます。
当院では医師・看護師・公認心理師・臨床心理士・精神保健福祉士・作業療法士などの専門職三十数名のスタッフが、みなさまを一人の「歴史ある人間」としてとらえ、専門家としての助言を行いながら対等な立場で「生きる」ことをサポートします。
そして、みなさま一人ひとりが人生の旅を続けられるように、メンタルヘルスの面からサポートすることができるように尽力する所存です。
よろしくお願い申し上げます。
NEWS & TOPICS
お知らせ・新着情報
2024-04-17
2024-04-12
2024-02-26
2024-02-14
TEL.048-831-0012
〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎4-2-25